
動物たちが住みやすい惑星を作り上げる、タイルゲーム『プラネット・メーカー』を遊びました。
子どもやボードゲーム初心者にも勧めやすい、2人~4人用のゲームです。
ゲームの概要
メカニクス的には、オープンドラフト、タイル配置、マジョリティと言ったところでしょうか。
全12ラウンドのゲームで、ラウンドごとに5枚のタイルが開示されます。スタートプレイヤから順に1枚ずつタイルをピックしていって、選んだタイルは自分の惑星コアと呼ばれる12面体のコンポーネントにくっつけます(タイルとコアの両方に磁石がついており、ぴったりくっつきます)。
プレイヤごとに、ゲーム開始時に目標カードが渡されており、たとえば森エリアを集めるだとか海エリアを集めるだとかの指針が与えられます。また、より多くの動物を、その惑星に住まわせることで勝利点が得られます。
ゲーム終了時、惑星コアの12面すべてにタイルが張られることになり、最も勝利点が高いプレイヤがゲームの勝者となります。

- 出版社/メーカー: アークライト(Arclight)
- 発売日: 2019/06/20
- メディア: おもちゃ&ホビー
- この商品を含むブログを見る
ゲーム中の風景

こちらは2人プレイのセットアップを終えたところ。
ラウンドごとに配られるタイルは山札になっており見えませんが、動物カードはすべて公開されています。たとえば、この状況だと3ラウンド目に熱帯魚が、4ラウンド目にアルパカが、5ラウンド目にヘビが出てくることになります。
ゲームの後半になるにつれ、多くの動物が出てきます。

こちらはゲーム中の風景。
ラウンドの頭に、5枚のタイルを公開し、スタートプレイヤから順々に1枚だけ選んでいきます。選んだタイルは、自分の惑星コアに貼り付けることで、自分の惑星を完成させていきます。
全員がタイルを選び終えたら、次は動物カードの獲得に移ります。
全プレイヤの惑星を見比べて、もっともその動物が住みやすい環境を構築しているプレイヤが、勝利点として動物カードを獲得できます。
「住みやすい」というのは、エリア数等で区別され、たとえば写真の中央奥に見えているキツネは「雪原に接している森林エリアが最多」の惑星を持っているプレイヤの元に行きます。ちなみに、その右側のリスは「雪原に接していない森林エリアが最多」となります。バツ印の有無で判断するわけですね。
最多エリアが同値の場合、そのラウンドでは引き分けとなり、動物カードは先送りされます。

ゲーム終了時の風景。
今回の目標カードは海だったので、なるべく海エリアを含むタイルを獲得したいところだったのですが、たとえば海が目標の場合、海に住まう動物カードを獲得しても1点にしかならないのに対し、海以外に住まう動物カードは2点になります。なるべく海エリアを集めたいのだけれど、海以外に住まう動物が好む地形も揃えたい……と相反する欲望に挟み込まれます。
ゲームの感想
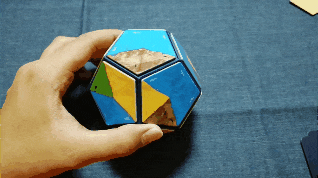
なんと言っても立体配置! これでしょう。
同様のゲームで言えば、たとえば『モンド』や『キングドミノ』など、類似のメカニクスを持つゲームがいくつか思い浮かびますが、正12面体のコンポーネントを持つゲームは、他に類を見ません。
取り出した瞬間、テンションはめっちゃ上がります。
しかし、いざ遊び始めてみると、なかなか上手くいかないもので、普段、正12面体の物体を観察するなんて経験がまったくないもので、なかなか情報が頭に入ってこないんですよね。
惑星コアを、ひとつの方向から見ていると、反対側が、完全なる死角になるのも困りもので、一望できないがゆえに、今、自分が必要としているタイルが、どのタイルなのか、直感的に分からないのです。
でも、これはこれで楽しく、何度も何度も手のなかで惑星コアをぐるぐる回しながら眺めるのも悪くなく、そのうち直感的に分かってくる瞬間があって、認識力のレベルアップを感じます。
ゲーム的には、動物カードが、すべて公開されているのが良いですね。
他プレイヤとエリアマジョリティを比べ、1位のプレイヤだけが得点化できるのですが、ゲーム終了に至るまでの、すべての動物カードが公開されているので、計画がとても立てやすいです。
他プレイヤへの助言も行いやすいので、子どもや初心者と遊ぶのにもうってつけではないでしょうか。
一緒に遊んだぺこらさんのコメント
自分がどこにいるんだか、分からなくなるよね。数えたのか、数えていないのか、よく分からなくなるよ
12面体だから、真上から見ると同時に6面見えるじゃない? だから、まずは6面を見て、その後、ぴったり180度回転させて、反対側の6面を数えればOK!
手を離した瞬間に、どこがどこだか分からなくなっちゃうよ
気合で慣れるしかないね……
タイルが全部、磁石だったから、冷蔵庫に貼りたくなるよね
ならないよ
そう?
終わりに
感想のところにも書きましたけれど、やっぱり12面体のコンポーネントが強いゲームですね。こんなの他に見たことがありません。
「このゲームを遊びましょう」と言って、コンポーネントを見せた瞬間に、絶対、テンションが跳ね上がるゲームです。