
秋山です。3月から在宅勤務を続けていますが、営業という職種であるため、ときどきではありますがテレビ会議では済ませられず、お客様の元を訪ねる必要が出てきます。
そういった事情で、約5ヶ月ぶりに渋谷に行きましたので、気になっていた落合陽一展『未知への追憶 -イメージと物質||計算機と自然||質量への憧憬-』を見てきました。
落合陽一を知ったきっかけ
恥ずかしいことこの上ないのですが、落合陽一を知ったのは2017年11月19日、情熱大陸で氏の特集が組まれた後のことです。
Twitterでカレーをストローで食う男という触れ込みで切り取られた動画を見て、得心しました。効率の極みです。
その後、現代の魔法使いという魅惑的なフレーズに導かれるように、氏の業績や活動を追いかけてみると面白いこと面白いこと。『日本再興戦略』も読みましたし、noteも追っていますし、YouTubeも見ています。
なかなか熱心なファンと言えるかもしれません。

- 作者:落合陽一
- 発売日: 2018/01/30
- メディア: Kindle版
未知への追憶
今年の5月に開設されたYouTubeのチャンネル落合陽一禄のサブタイトルとも言える「未知への追憶」この言葉に込められた意味は第1回にて語られています。
また、個展『未知への追憶』については、こちらで語られています。
と言うわけで、事前にこれだけチェックしてしまうくらい、期待を抱いて足を運びました。
会期は7月23日から8月31日までの約1ヶ月間。
会場は渋谷モディの2階です。
感想

いきなりなんですが、会場についてから、仕事鞄に財布がないことに気が付きました。
他の美術館や展示会ならまだしも、他ならぬ落合陽一展だからキャッシュレス決済には、きっと対応しているだろうと思いつつ、受付の方に声を掛けたら、現金とクレジットカードに対応ということで、救われました。
1800円の一般入場料を払おうとすると、特典付きチケットを勧められ、しかも「今なら落合さんのサイン入り限定トートバッグがありますよ。昨日いらっしゃって、サインを残されたんです」と言われ心がざわめきましたが、貧乏性なので断わってしまいました。ちょっと後悔?

映像や静止画による落合作品は、今まで見てきましたが、リアルに目の前に存在するアート作品としての物体を見たのは初めてでした。
ウィズコロナ時代の展示ということで、会場の一角にはQRコードが貼られており、読み取ると限定公開のYouTubeに飛ぶことができます。内容は落合陽一自身による作品の解説やその来歴。
たとえば『アリスの時間』について、SEKAI NO OWARIのライブ会場を担当したなんて逸話もあって、これが無料で聞けるのはお得以上の何物でもないですね。

660平方メートルという渋谷モディ2階を使い、メディアアート作品40点以上が展示されています。
各作品は手掛けた年代やテーマによって分類されており「映像と物質」「物質と記憶」「情念と霊性」「風景論」「風景と自然」「質量への憧憬」「共感覚と風景」と命名されています。

どれも興味深く「やっぱりリアルで見ると違うな」であるとか、「好きなタイミングで、好きな角度から見られるのはいいな」であるとか、ありきたりな感想しか抱けませんでしたが、圧倒的に足を止めさせられたのは「質量への憧憬」ですね。

最初に録音したテープを再生し続けて、会期を経て劣化していく様を見る作品は、最初に見たときはピンと来ませんでしたが、QRコードを読み取って説明を聞いたら納得しました。
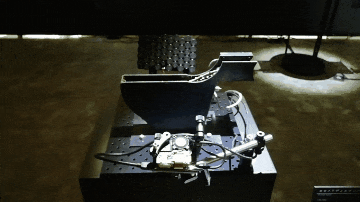
超音波ディスプレイは、見た瞬間は意味不明でした。
けれど、見ているうちに、そう言えば空気を光らせたり、映像を浮かび上がらせる研究をしていたけれど、その成果がこれなのかなと思い至りました。このコーナーはいずれも興味深く、「質量とは? それに対する憧憬とは?」と考えながら見続けてしまいました。

残念ながら、QRコードによるコメントでは、さっくりと流されてしまいましたが、私の心を、もっと強く掴んだのは、デンソーのロボットです。
大量の写真のなかから、どれを飾るべきか、逡巡し、迷いつつも一葉を選び、一定時間、見せたと思うと、さっとしまいこんでしまう。明らかに写真を見られる時間よりも、思い悩んでいるロボットを見ている時間の方が長いです。
その隣の、大量の写真を流しつづけるブラウン管もインパクトがありました。大量の写真を、凄まじいスピードで表示しているのですが、ときおり妙に刺さる写真があるんですよね。でも、1秒に何枚もの写真を見させられるほど高速に切り替わるので、どの1枚も、じっくり落ち着いて隅から隅までは見られないのです。
瞬間的に視界に飛び込んで「あ、今の良かった気がする」と思っても、その頃には切り替わっているわけで、ただ、網膜に残滓のように残った面影を追い求め──
これが追憶か
と身を持って体験させられるわけです。
写真の出自は不明ですが、おそらく落合陽一自身が撮ったものでしょう。であれば、切り取られた写真は、彼の追憶であって、私の追憶ではないはずです。
共感覚。は、最後のテーマです。

地味に好きなものとして、ステートメントを挙げさせてください。
公式サイトで全文が読めますので、ここでは冒頭と最後の数行だけ引用します。
質量と物質、ボケと精微、
https://www.0101.co.jp/michi2020/
映像のようでいて物質であるもの
幽かでいて玄なる根源に近づくもの
(中略)
文脈を漂白し、記憶も情念も漂白しながら、
無為に近づく意識が整うまで反芻し、
忘却の中で未知を追憶し続ける。
なんとなく森博嗣のポエムを思い出す、のは私だけかもしれません。
ですが、これを読んだとき、すとーん! と理解できた気になりました。
私が感じ取ったのは、相反する、あるいは共生する概念です。言葉、と言い換えてもいいかもしれませんが、まず言葉があって、その言葉の背景にある歴史や経緯みたいなものを考えつつ、それに相反する、あるいは共生する言葉を拾ってきて、それをぶつけてみたりして、どういう化学反応を起こすか見てみる。
落合陽一がやっているのって、つまりは、そういうことなんじゃないかな? と感じた次第です。
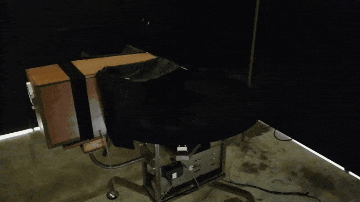
物販コーナーで本があったら買おうと思ったのですが、ありませんでした。
上述のステートメントが書かれたマフラータオルは、ちょっと心惹かれましたが「ライブかよ!」という内なるツッコミに負けて買いませんでした。
そう言えば、少し前に「オタクはクリアファイルやポストカードは使うのではなく飾る」という言説を見て、目からウロコでした。なるほど、確かに額縁に入れて飾れば立派な作品です。部屋にアートを飾り、日常を潤す。というのは、いずれやってみたいことのひとつです。
終わりに
時間がなかったので鑑賞することに全力を注ぎ、メモを取らなかったことを少し後悔しています。
作品を見た瞬間に脳裏に宿った閃きだけは瞬間的で得難いものだから必ずメモを取るようにと肝に銘じていたはずなのですが……。
と、個人的な反省はありますが、とても良い空間でした。夏休み、渋谷を訪れる予定のある方は、是非。